透析から移植、そしてオストメイトになった私の体験談腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ
【第5話】出口の見えないトンネル〜膀胱直腸瘻の治療【中編】
2023.2.27
緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。

前回の膀胱直腸瘻の治療【前編】で入院期間が1年に渡ったことに触れましたが、その1年間の出来事について詳しくお話しします。
■移植した腎臓を守るために難航した治療
人工肛門を造設したことで一時は体調に改善の兆しが見られましたが、1日おきの発熱と慢性的になってしまった足腰の疼痛に悩まされ、造設からおよそ3カ月後に再入院となりました。
再入院で行った治療は、発熱などの原因となっている膿瘍(膿が袋状に溜まったもの)の排出と、その膿瘍の原因である膀胱の穴の処置の2点でした。
膿瘍の排出については、軽度の場合はCTスキャンや超音波検査で画像を見ながら穿刺を行って膿瘍を排出し、残りの膿が排出されなくなるまで細い管を留置して様子を見るものでした(入院中、私はこの方法を針刺しと呼んで恐れていました)。
重度になると、手術で直接膿瘍を除去することになります。
どちらの治療方法も、抗生物質の投与とCRP(体内で炎症などが起きた場合に増える蛋白質) や白血球といった炎症反応に関連する数値とクレアチニンの数値を注視し、管を抜く時期や抗生物質の中止時期を判断します。
私の場合、免疫抑制剤の影響で炎症反応の数値が下がらず、下がらないからといって移植した腎臓のために免疫抑制剤は絶対に止められない、という相反する状況が起き、治療は難航しました。
一方、膀胱の穴の処置については、手術で塞ぐこと自体は技術的には簡単でした。腎臓移植手術の時点で膀胱の組織が脆いことが分かっていたので、当初は手術に踏み切れないという事情がありましたが、「この状況を何とか脱したい」という一心で、手術を受ける決意をしました。2000年12月5日に手術を受け、膀胱の穴をふさぐと同時に溜まった膿瘍の除去も行いました。
手術後はとにかく膀胱の穴が閉じることを願いながら体力の回復に努めましたが、状況は一進一退。なかなか改善の兆しが見えないまま年が明けました。
肛門と膀胱の両方でストーマの造設が必要に
年明けから2週間ほど経過したある日、主治医から「最後の手段として尿管皮膚瘻を考えています。すぐに答えを出す必要はありませんが」と告げられました。
尿管皮膚瘻とは人口膀胱の一種で、腎臓に繋がれている尿管を直接体外に出し、パウチにつないで尿を排出します。その処置を行うことで膀胱を全く使わない状態にして、膀胱の穴が塞がることを期待するのです。つまり直腸と同じ状態を膀胱でも行うことになり、主治医からの提案は一時的とは言え「ダブルストーマ」になることを意味していました。
主治医の説明によると、私は免疫抑制剤を服用しているため膀胱直腸瘻の治療自体が難しく、病院の内外問わず多方面の意見を聴いた結果、この方法が最善となったようです。
そして、最終判断すべきタイミングの前に日本移植学会に出席する機会があるらしく、そこでもう一度他にも最善の方法がないか意見を聴いてから判断するということになりました。
初めて主治医からこの治療の提案を聞いた時は現実として受け入れられませんでした。
「排泄行為の両方を自力でできなくなるのでは、腎臓移植をした意味があったのか?」と自問自答し悩みましたが、一方で信頼している主治医の判断を受け入れたい気持ちもありました。
結局、日本移植学会での反応は主治医の見解と同じだったようで、2001年1月30日に尿管皮膚瘻の造設手術を受けました。
術後は、自分の体がどうなっているのか怖くて見られない日が続きましたが、出来得る限りのことはやったので、あとは体調が良くなることだけを期待していました。
しかし、その期待とは裏腹に、この後退院までに手術を2度受けなければならない状況となるのです。
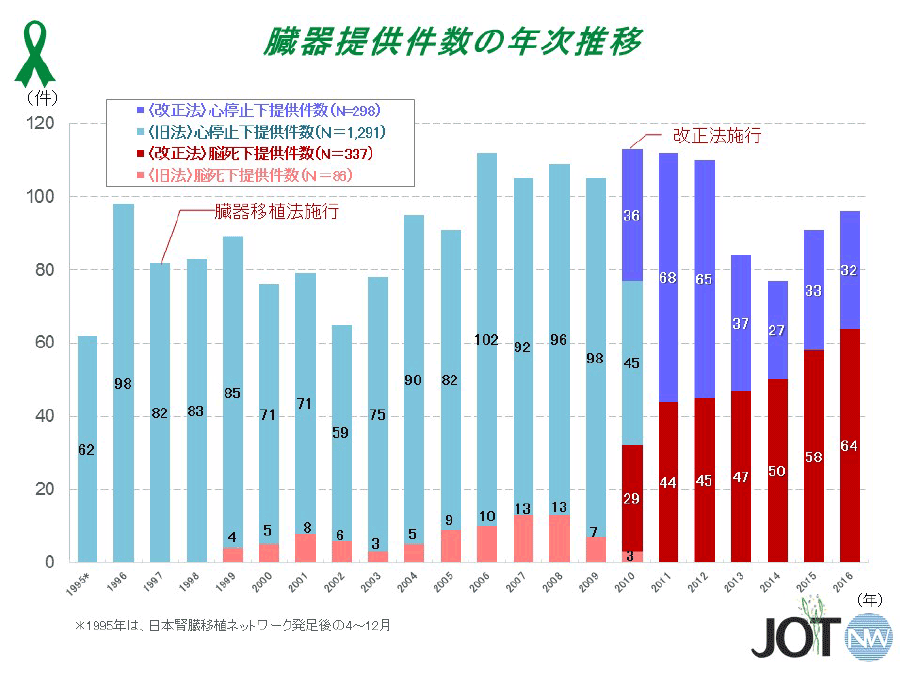
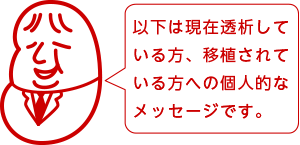



ご意見をお寄せください